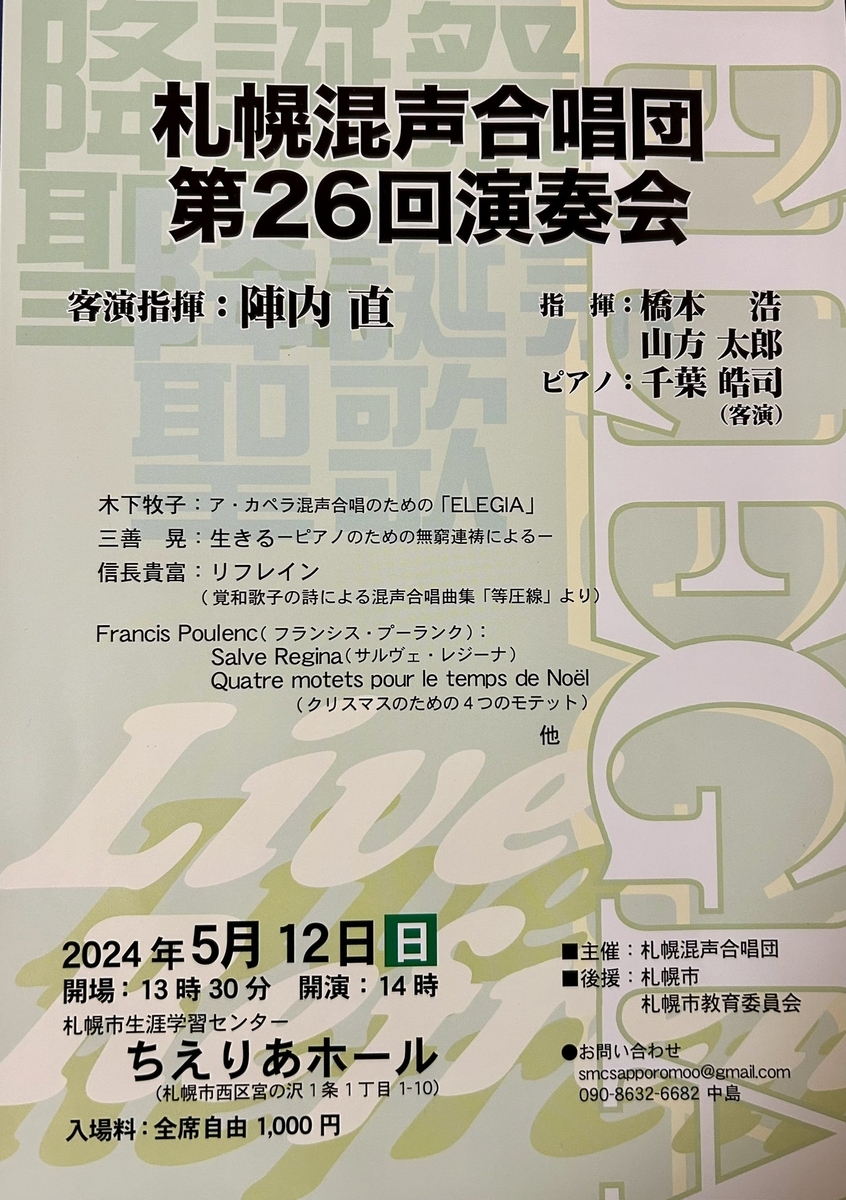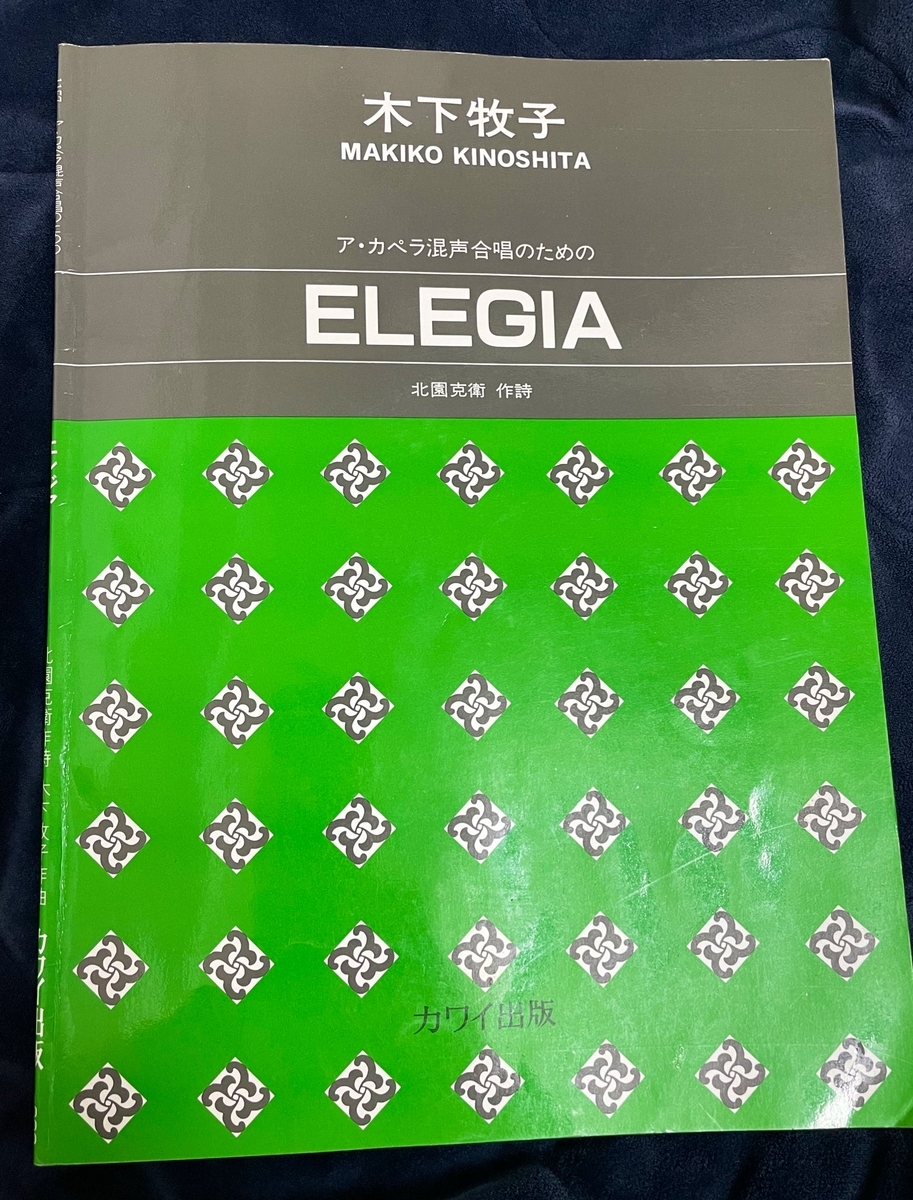前回の「大学オンライン合唱祭で頭を抱えたこと(1/2)」を先にお読みください。
まず1つ目の【求められていないアドバイス】
1)全団体を俯瞰して、主催者側がお勧めしたら?
26団体の参加は素晴らしいけど、視聴者が26団体ぜんぶ聴くのは正直大変じゃないですか。
だから投票前、カテゴリー別に3団体ずつ選んだら、その団体の注目度が上がるし、結果多くの団体が聴かれることになるのでは?と。
例えば
《団員数が少ない団体ランキング!》はどうでしょう?
第1位、群馬大学混声合唱団さん 10人!
表現者として一人一人が自立した音楽でした!
第2位は東京大学音楽部女声合唱団コーロ・レティツィアさん、東京大学音楽部合唱団コールアカデミーさんが13人!
レティツィアさんは貴重な女声団体、演奏も緊張が満ちる高度なもの。
コールアカデミーさんは気持ちが入った愛唱曲の演奏で心地良かったです。
……という風に。
他に、最近の邦人合唱曲を選曲される団体が多かったので
《珍しい選曲の団体ランキング!》とか。
第1位、甲南大学文化会グリークラブさん!
フィンランドの作曲家Ilkka Kuusistoを初めて知ることが出来ました!
第2位、京都大学音楽研究会ハイマート合唱団さん!
フランスの作曲家:フランシス・プーランクの悔悟節のモテットも、悲痛な想いとプーランク特有の音楽を巧みに表出していました。
第3位、東北大学男声合唱団さん!
「South Rampart Street Parade」はバーバーショップ的なノリが、歌と動きへ良く出ていました。一見の価値あり!
とか。
「聴かれにくい団体を、カテゴリー別に選び注目されるようにしよう!」って。
・・・そこで返ってくるわけですよ。
「じゃあ自分でやってみたら?」
やってみましょうか、全国大会出場の大学ユース部門だったら
《団員数が少ない団体ランキング!》
昨年の合唱コンクール全国大会の大学ユース部門では
第1位、愛媛:Female Ensemble Mandaeliteさんの9名、
第2位、東京:なにやらゆかし合唱団さんの24名
第3位、兵庫・Man de rartさんの27名。
《珍しい選曲の団体ランキング!》
海外曲を選んだのは
関西学院グリークラブさんの「GAGÒT(Sydney Guillaume)」
混声合唱団名古屋大学コール・グランツェさんの「O magnum mysterium(Chris Artley)」「Alleluia(Jake Runestad)」か~。

う~ん……でも考えてみれば邦人作品だけど、都留文さん演奏の津田元作品も最新の曲で珍しいし、北大さんの三善晃「薔薇よ」もコンクールでは珍しいし。
そもそもですね、このカテゴリーの分けかたは効果的なの?
注目の団体へ、さらに耳目を集めていないかな??
難しい!すいませんでした!!
と自身の浅い考えを反省することになってしまったわけです。
・・・次行ってみましょう。
2)スポンサーを募り特徴的な賞を創ってみたら?
大学合唱オンライン祭では、「合唱祭グランプリ(総合点1位団体)」
(総合点→視聴者投票と参加団体相互投票の得票数を7:3で得点換算し算出)
「東北大学賞(視聴者投票1位団体)」
「フェスティバル賞(参加団体相互投票1位団体)」
「特別賞(再生回数やコメント数)」と4つの賞があります。
最初に書いたように参加団体相互投票はとても良いアイディアだと思いますし、グランプリにもその票が活かされるのも良いですね。
4つも賞があればいろいろな個性の団体に光を当てる機会になりそうです。
ただ、4賞のうち3賞は「上智大学混声合唱団アマデウスコール」さん受賞になってしまって。
(特別賞の再生回数が多い団体は北海道大学合唱団さん、視聴者からのコメントを多く集めた団体は東北大学男声合唱団さん)
アマデウスコールさんは自分も「最高にお勧めします!」と書いた団体なだけに異論は全く無いのですが、この投票条件だと賞すべてが似通ってしまいそうな。
2つめの【求められていないアドバイス】いってみますね。
東北大学の学生さんが主体となっているので、仙台市の企業でスポンサーを募り
【特徴的な賞を創り、ユニークな賞品を出してもらったら?】
例えば
「ヘアサロン △△アトリエさんから『△△賞』として" 一番目立ったプレイ ”に《ヘルスケア・コスメセット》をプレゼント!」
「ワインと地酒 ○○屋さんから『○○賞』として" 一番まじめな演奏 ”に《極上日本酒一升瓶》プレゼント!」
「こんな性質の賞」と規定することで、得票数で決まってしまう賞との差別化が図れるんじゃないかな?
あと、「スポンサーの○○さんは学生時代、合唱団でバスパートリーダーをやっていたので【縁の下の力持ち的な演奏】が大好き」
そんな背景があると賞そのものに個性が出て面白いですね。
さらに「ユニークな賞品によって、合唱祭の認知度を高める」、そんな効果も見込めると思って。
「大学合唱オンライン祭」と宣伝するだけじゃ無く、「賞品に日本酒があるんですよ!」みたいな話のきっかけがあれば注目を集めやすいのでは?
「じゃあ自分でやってみたら?」
……やってみましょうか。
すみません、最初から謝ってしまいます。
ぶっちゃけ、企業の窓口や、自営業社長さんとのお金が絡んだやり取りはなかなか難しいんですよ。
知り合いやOBならまだしも、新しいスポンサーを簡単に開拓できるのか?
有り難くスポンサーが決まったとして、賞の選定も「名前だけ貸していただき、賞は主催者側で決めますから」に難色を示す方がいらっしゃるかも。
スポンサー自ら選んでもらったとしても、スポンサーの出身大学や知人繋がりのひいきで、主催者側の思惑とまったく違うものになったら?
あと「ユニークな賞品」、遠方の大学が選ばれたとして、賞品を送る【送料】も、ちゃんとスポンサーからいただいているんだよね?
・・・う~ん難しい!またしても浅はかな思い付き!
すいませんでした!!
いやもう
他者が『こうすればいいのに』と思う時
そこにはできない理由がある

はまさに至言ですね。
他にも合唱祭独自のハッシュタグが無いので、「ひょっとしたらSNSで騒いで欲しくないのかな?」と邪推したら、主催者さんから完全否定されたり。そもそもX(旧:ツイッター)のインプレッションが急激に下がり以前より多くの人には見られなくなっている現在、ハッシュタグはどこまで効果があるのか。じゃあ他のInstagramやFacebookなどのSNSの方がイベント情報を広められるのでしょうか?新しいSNSもそれほど人が集まっているわけではないだろうし。あとコンクール観客賞では、投票と同時に推薦のコメントも視覚化されるので、オンライン合唱祭も結果発表後にコメントを見ることが出来れば良いかなぁ……と思いましたが、コメントに意見が引っ張られることもありこれも一長一短。さらにこういう「いつでも動画を観ることが出来るイベント」の場合、演奏者と自分以外の観客が同じ時間を共有していると感じにくく、どうしても求心力が少なくなります。ニコニコ動画のコメントはそういう非同期性を補うものとして当時話題になったわけですが、「いまさらニコニコ?」だし、他のシステムで何とか補完できないものか。そもそも歌うことを目的として集まった合唱人たちへ「聴かせる」ことが難易度高いし。演奏を聴いてもらっても、その先の投票したり感想コメント書いたりに喜びを感じてもらうにはどうしたら?「投票してくれた方に抽選でプレゼント!」も安易だし。多種多様な観客が「この団体めっちゃ良いよ!」といろいろ推しまくり、【イベントが活性化する流れ】はどうやったら作れるのかな〜?とか・・・
すいません!
自分もずっと悩んでいて、答えが出ないことなのでボヤいてしまいました。
ただひとつ、アドバイスでは無くひとつだけ「お願い」として記すなら。
『続けて欲しい』
……んですよね。
今までの害悪なアドバイスは一切無視してもらって構わないので。
「第2回」、「第3回大学オンライン合唱祭」と、数字が増えていって欲しい。
だって続けていくうちに得られるものが絶対あるはずなんです。
こういうネットのイベントは、ネット内で盛り上がるのはもちろん楽しい、だけど。
その先にある面白さは、「ネットを超えたリアルに影響すること」だと思うんですよね。
イベントの閉会式で、全体講評として山脇卓也先生がとても良いことを書かれていました。
引用します。
例えば、この試みを足がかりとして気に入った合唱団とコンタクトをとって、演奏旅行などしてみてはどうでしょうか?
一緒に歌い、一緒に飲み、語り明かし、また悩みを共有する。
そんな人の存在はとても大きいですし、一生語り合える経験になること間違いありません。
山脇先生の実感のこもった、凄く良い言葉だと思います。
大学オンライン合唱祭がずっと続いていくことで、地域の枠を超え、他合唱団とつながるきっかけとなる。
そんな風にネットを超え、リアルの世界へ影響を及ぼすイベントとなれば本当に素晴らしいですね。
いま主催者さんも「第2回大学合唱団オンライン合唱祭 主幹合唱団募集!」と次回へ向け動かれているよう。

また来年の
「第2回大学オンライン合唱祭」
楽しみに待ってますよ!
(おわり)